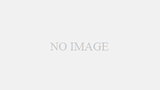あなたが法律の専門家を選ぶとき、優先する判断基準は何ですか?
世の中には沢山の法律の専門家の事務所がありますが、誰に頼んだらよいのか迷われることも多いと思います。
当然、人間同士ですから、相性があるのは当然です。
本コラムでは、簡単に事務所の歴史について説明させていただいた上で、当事務所の基本的な案件受任スタンスについて、ご紹介いたします。
事務所紹介
当事務所は、2022年に江東区の門前仲町(もんぜんなかちょう)で開業しました。
場所を江東区にした理由は、行政書士の中でも珍しい企業法務を扱う事務所であったため、都心に近い方が好都合だったこと、周辺に行政書士事務所や法律事務所が少なく、競合が少ないと考えたからです。
多くの行政書士事務所は、自身の「苗字+行政書士事務所」という形式が多いのですが、それでは広報活動がしにくいと考え、地域の名称である「深川」を事務所名に入れ、周辺の事務所と名前が重複しないよう、「東京」を加え、「東京深川行政書士事務所」としました。
2023年の春に台東区のぱんだ行政書士事務所と合併し、ぱんだ行政書士事務所のロゴやブランドイメージを引き継ぎながら、両事務所の良いところを残し、現在に至ります。
2023年の夏以降は、行政書士だけでなく、他の士業の方々や、デザイナー、イラストレーター、ライター、秘書の方にも参画をいただき、江東区や江戸川区、墨田区といったいわゆる城東地域の行政書士事務所としては、最大規模級の体制となりました。
基本的には、普通に生きていれば遭遇する、あるいは巻き込まれる事案、離婚や相続といった事案(一般民事)を取り扱いながら、企業法務全般、許認可取得・維持、刑事告訴、行政事件関係を扱う総合事務所です。
中でも特筆されるのが、刑事告訴や行政事件を扱っている点です。
2022年以降、20件近く刑事告訴を行いましたが、現時点での受理率は100%を維持しています。
過去に担当した事案の紹介では、いわゆる著名事件や大きな事件はありませんが、社会的に悪質な事案は、テレビや新聞で報道されたものもあります。
また、個人開業が多い行政書士が、複数所属しているのも珍しい点です。
お客様は、大手企業からのご依頼もありますが、当事務所がスタートアップの企業や個人事業主を特に得意としていることもあり、どちらかというと、小さな事件をこつこつとやっているのが普段の姿です。
知識、経験、能力を優先するという方は、当事務所の各コラムをご覧いただき、ニーズに合うかご確認ください。
当事務所は、相対的に安め、あるいは業界標準の価格設定をしているつもりではありますが、もちろん業界最安ではありません。
また、安さを売りにするつもりもありません。
安さが最優先なら、それを売りにしているところをお探しいただきたいですし、行政書士の価格比較サイトを利用すれば、リスクと隣り合わせではありますが、業界相場を大幅に下回る価格で依頼することができます。
相談から、ご依頼までの流れ
当事務所へご依頼いただくまでの通常は、まず当事務所に所属する法律の専門家と相談し、事実関係と相談者の意向、案件処理方針を確認します。
お話や裏付けとなる資料の内容から、その時点での手続や事案の見通し、現実的に可能な手続と主張の基本的な方向性、手続にかかる期間とコスト等をご説明し、ご納得の上で「依頼したい」という話になりましたら、契約書を作成し、正式に案件を受任いたします。
進め方や方向性、期間やコスト等をご説明し、それについて十分にご納得いただいて初めて契約締結となります。
相談の結果、「依頼しない」という選択も問題ございません。
この段階で費用が発生することは、特殊な事案を除き、通常はございません。
相談は、事前に10分程度お電話で打ち合わせの上、直接あるいはオンラインでの面談が最も良いと当事務所では考えております。
よく、初回の電話の段階で「費用を教えてほしい」と端的な見積もり依頼をいただくこともありますが、面談では、一般的な手続や法律知識を話すだけではありません。
それぞれの相談者の方の事情をお伺いして、その事情にあわせて、相談者の方の希望する解決に近づく方法を検討します。
相談者本人から、具体的に事情を聞かせてもらわないと、ほとんどの場合、適切な回答はできません。
例えば、飲食店を営業したいという行政手続の場合、相談者の方の状況を法令等で定める要件(基準のようなもの)に合致しているか確認し、必要な書類等に当てはめて結論を導きます。
つまり、法律の専門家は、ヒアリングをするだけでなく、状況を法令等の規範に当てはめて、その結果、求める結論に導けるかを判断する作業を行います。
また、大抵の法的論点では、書類が重要な役割を果たします。
ですから、当事務所との初回の電話では、大まかな内容をヒアリングし、専門家は面談時に必要な資料の用意をお願いし、それらをお持ちいただくのが通常です。
稀に、電子メールやチャットのみでの相談を希望される方もいらっしゃいますが、当事務所では原則として導入しておりません。
まず電話でだいたいの相談内容を確認するのは、ご用意いただく資料をお伝えしたり、緊急度合い、相談や案件にかかりそうな時間を判断し、その後の相談を充実させるために必要不可欠だからです。
手続一つでも、事情は個々に異なり、案件終了までの工数も様々ですので、最初の電話だけで見積もりが出せないのは、そのためです。
よく、他の行政書士や司法書士、弁護士と業務範囲や金額面でトラブルになり、その相談をいただくことがありますが、これらのトラブルは、案件依頼前に、専門家と十分な相談をしていないことに起因します。
ご相談、ご依頼時の留意点
行政手続は、期日があることが多いため、時間に余裕を持ってご相談ください。
一つの申請を行う場合、よほど簡単な手続でない限り、3日から10日程度かかることが一般的です(書類作成から申請まで)。申請期限ギリギリで相談いただいても、明らかに間に合わないことが予想され、やむを得ずお断りすることもあります。
期限間近のご依頼は、トラブルが多いのも特徴です。
許認可を必要とする事業を営んでいる方は、何かあった時に、常日頃から相談できる行政書士が2〜3名いると安心です。
また、各専門家は、決まった時間に事務所にいるというわけではありません。
特に当事務所の場合は、日本全国、場合によっては海外からのご依頼もありますので、事務スタッフを除いて全員が外出していることも珍しくありません。
もちろん、外出中の場合でも、いつ事務所に戻るかは、事務員が把握しています。
事務所にいる場合でも、打ち合わせをしていたり、通常、事件の記録や証拠などを検討しているか、申請書類を作成しています。
当事務所としては、営業時間をなるべく広くし、年中無休にし、混雑を緩和するよう努力しておりますが、各専門家は、平時の場合、約50件近い案件を常時担当しているため、あまりにも急な申請には、応じられないというのが通常です。
各専門家の執務パターンは、平日日中は電話や来客、行政庁の対応、平日夜には集中して行うまとまった書面作成が一般的です。
事務所自体は年中無休ですので、代表を除いて各専門家は適宜休みを取っています。
各専門家には、貴重なオフタイムを完全にオフにしてほしいと考えているため、休みの日は、よほど緊急でない限り、その日のメールの返信は行わないよう徹底しております。
大事な案件は、代表や他の専門家をCCに入れ、代わりに対応するのが当事務所の通常の運用です。
法律の専門家への相談は、事前にメモがあればスムーズです。
最近、法律相談に来られる際に、相談内容について、事前にメモを作ってくださる方が増えています。
相談する側にとっても整理になりますし、相談を受ける側も、適切なメモがあると、相談しやすくなります。
長い期間にわたって様々な出来事があった場合、時系列に沿って箇条書きにしてあると、一番重要と思われる事柄に、重点を置いてお話いただきやすくなります。
また、メモはA4用紙2枚程度に纏まっていることが望ましいです。
位置関係や人物関係が複雑な場合は、事前に関係図にしてあると、当日の面談が非常にスムーズですし、お互いにイメージが一致します。
まとめ
本コラムでは、事務所の歴史について説明させていただいた後、ご依頼までの流れや、相談メモのポイントについてお話しさせていただきました。
特に相続関係は、事前のメモや人物関係図があるだけで、当事務所からの質問数を減らし、より重要な内容に重点を置いてご説明できますので、簡単で結構ですので、事前にご用意いただけますと幸いです。
お問い合わせはこちらから!