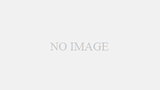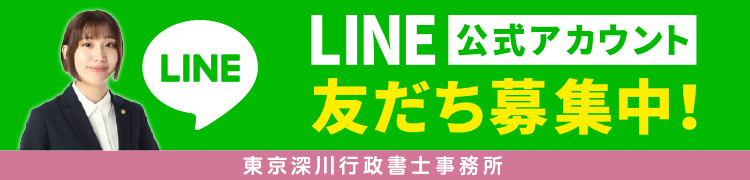はじめに
「行政書士としてもっと踏み込んだ業務を担当したい」
「申請だけでなく“不許可”や“行政処分”にも対応できる力を身に付けたい」
そんな行政書士のステップアップ資格が、「特定行政書士」です。
通常の行政書士は許認可申請が主な業務ですが、特定行政書士になると、行政処分に対する不服申立て(審査請求など)を代理人として行えるようになります。
本記事では、特定行政書士になるための具体的な手順(研修・考査)、研修内容、試験対策、そして実務での活かし方まで、実体験も交えて詳しく解説していきます。
特定行政書士とは?制度の概要
行政書士との違いは「代理権」
通常の行政書士は、申請や書類作成のプロですが、「許可が下りなかった」などの争い事に代理人として関わることはできません。
しかし、特定行政書士は、行政不服審査法に基づく審査請求などの“法的代理人”として行動できるのです。
✅ 対応可能な業務
- 許認可の不許可に対する審査請求の代理
- 行政庁との文書提出、主張・立証活動
- 審査庁に対する意見陳述
これは、2014年(平成26年)6月の行政書士法改正により創設された制度です。
特定行政書士になるには?|必要な手続きと資格要件
- 行政書士登録が前提
まず前提として、特定行政書士になるには、すでに行政書士として登録されていることが必要です。未登録の受験生は、合格後に行政書士会に登録してからしか挑戦できません。
- 日本行政書士会連合会が実施する「特定研修」を受講
この研修は、法律の基礎から実務対応までを幅広く扱います。主な内容は以下の通り:
- 行政不服審査法、行政手続法の体系理解
- 審査請求書・主張書面・証拠資料の作成実習
- 想定事例に基づく意見陳述のロールプレイ
✅ 研修時間:全体で約30時間程度(オンライン+スクーリング)
✅ 期間:おおむね2~3か月程度
- 修了考査(筆記試験)に合格する必要がある
研修終了後に行われる修了考査に合格して初めて「特定行政書士」と名乗ることができます。
出題形式は記述式が中心で、実務的な判断・表現力が問われます。
✅ 主な出題分野
- 行政不服審査法
- 行政手続法
- 行政事件訴訟法(基礎的理解)
- 実際の申立書・陳述書の記述演習
合格のための勉強方法とコツ
法律条文の理解だけでは不十分
法律そのものの知識は当然必要ですが、試験では「事例にどう対応するか」という実務感覚が問われます。
そのため、以下のような学習法が効果的です:
- 過去の申立書や裁決例を読む
- 研修中の演習問題に真剣に取り組む
- 事例ごとの“落としどころ”を考える習慣をつける
✅ 体験談:40代・実務経験3年の行政書士が語る「特定研修と考査」
「座学だけでは分からない“争いの場”の感覚を知れるのが大きかった。行政庁との交渉経験がある人ほど、研修内容は腑に落ちると思う。考査も、実務的な視点を持っていれば怖くないです」
特定行政書士になるメリットとは?
許認可+不服申立て=一貫対応が可能に
通常の行政書士の場合、「不許可になったら、そこからはご自身で対応してください」というしかありません。
しかし、特定行政書士なら、申請から審査請求まで一貫して対応可能です。
これにより、依頼者からの信頼度が高まり、結果として顧問契約や継続依頼につながることも多くなります。
✅ 事例:医療法人の行政処分に対応→顧問契約を獲得
特定行政書士となったBさんは、医療法人から「施設運営に関する改善命令」への対応を依頼されました。
行政庁との交渉を重ね、業務改善報告書と再発防止策をまとめた結果、処分が軽減。
法人側からの評価が高まり、年間顧問契約に発展したとのことです。
差別化・収益アップにもつながる
「行政書士は競争が激しい」と言われますが、特定行政書士は全国的にもまだ少数派。
対応可能な領域が広がることで、自然と単価が上がり、依頼件数も増えやすくなります。
まとめ|本気で行政実務に向き合うなら特定行政書士を目指そう
特定行政書士は、「申請を通すだけではなく、争う力も持つ」数少ない法律系専門家です。
- 研修+考査をクリアする必要はありますが、行政実務に携わってきた方には納得感のある学びとなるでしょう。
- 許認可トラブルに最後まで伴走できる存在として、依頼者からの信頼も厚くなります。
「行政と戦える行政書士になりたい」と思ったとき、特定行政書士は確実にその一歩を叶える武器になります。