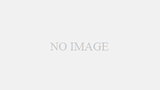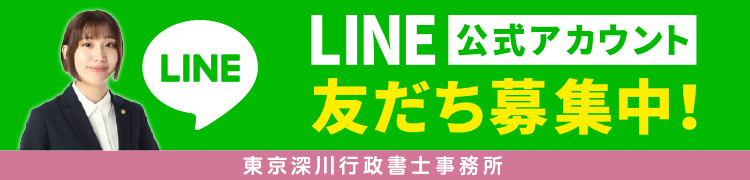1.はじめに 契約書の文言、なんとなく読んでいませんか?
業務委託契約を結ぶ際、契約書の中に「準委任契約」や「請負契約」という言葉を見かけたことがある方は多いと思います。しかし、「聞いたことはあるけれど、正確な違いまでは分からない」という方も少なくありません。実際、契約内容を正しく理解していないことで、納品後に「報酬が支払われない」「キャンセルされたのに損害が補償されない」といったトラブルが発生するケースが増えています。
東京都江東区にある【東京深川行政書士事務所】でも、契約トラブルのご相談を受ける中で「そもそも準委任と請負の違いを知らなかった」という声を多く聞きます。契約トラブルは、発生してから対応するよりも、未然に防ぐことが何よりも重要です。そのためにも、契約の種類と特性を理解し、正しく使い分けることが必要不可欠です。
この記事では、準委任契約と請負契約の基本的な違いと、契約時に押さえておきたいポイントについて、分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 準委任契約と請負契約の法的な違い
- よくある混同事例とそのリスク
- 契約時に注意すべき3つのポイント
2.準委任契約と請負契約のざっくり比較
準委任契約と請負契約は、いずれも民法に定められた契約類型ですが、根本的な性質が異なります。
準委任契約は「一定の業務を遂行すること」を目的とし、成果を保証するものではありません。たとえばコンサルタント業務や営業代行など、成果が不確実な業務に多く用いられます。実施した業務そのものに対して報酬が発生するため、成果が出なかった場合でも、業務を行っていれば報酬請求の権利があります。
一方、請負契約は「成果物の完成」が目的となる契約です。成果物の引渡しと引き換えに報酬が支払われる構造になっているため、ウェブ制作やライティング、アプリ開発など、納品物が存在する業務で使われることが一般的です。報酬の支払は、原則として成果物の完成が前提となります。
この違いを理解していないと、契約後に「仕事はしたのに報酬が出ない」「思っていた業務と違う」といった誤解や紛争に発展しやすくなります。業務委託契約を結ぶ際は、契約の性質と目的をしっかりと確認することが大切です。
3.よくある混同事例
ここでは、実際によくある3つの混同ケースを紹介します。
事例1 営業代行:「アポが取れなかったから支払いなし」と言われた
ある営業代行業務で、クライアントが「アポイントが一件も取れなかったので、報酬は支払わない」と主張したケースがありました。
この業務は「一定時間、営業活動を行う」という内容で、成果(アポイント取得)を保証していたわけではありません。つまり、契約の性質としては準委任契約であり、報酬は業務遂行自体に対して支払われるべきものでした。業務を行った証拠を基に請求を行い、最終的には報酬が支払われました。
準委任契約においては、成果の有無ではなく、業務を行った事実が報酬発生の根拠になります。クライアントとの認識のずれがトラブルの原因となるため、事前に「成果は保証しない」旨を明確にしておくことが大切です。
事例2 ライター業務:「構成まではやったのに報酬なし」
Web記事の執筆依頼で、「記事の構成までは作成したが、先方がキャンセルしたため報酬は出せない」と言われた事例です。
この契約が請負契約であるならば、成果物の完成が報酬支払いの条件となり、途中で契約が終了すれば支払い義務は発生しない可能性があります。しかし、構成作成などのプロセス業務に報酬が含まれる準委任契約であれば、作業した部分については報酬が発生します。このような場合は契約書の文言や業務内容の整理が重要です。
あいまいな契約内容がこうした認識の食い違いを生みます。契約書の中で業務範囲と報酬発生条件を明確にすることで、こうしたトラブルは未然に防ぐことができます。
事例3 ECサイト制作:「途中でキャンセルされたが報酬をもらえない」
ECサイト構築の途中で発注者から一方的にキャンセルされ、報酬を支払ってもらえなかったというトラブルもあります。
この場合、請負契約であればキャンセル時に一定の損害賠償や報酬が発生する可能性がありますが、準委任契約だと着手分のみの支払いにとどまることもあります。曖昧な契約内容のまま進めたことが、トラブルの原因となっていました。
契約書には「契約の途中終了時の取扱い」も記載しておくと安心です。業務の途中でやめざるを得なくなった場合でも、実施済みの業務に応じて報酬が発生するように設計することが望まれます。
4.契約時に確認すべき3つのチェックポイント
準委任契約か請負契約かを明確にすることで、後のトラブルを防ぐことができます。以下の3点を契約書に記載しておくことをおすすめします。
- 成果物の有無を明文化する
業務の目的が「成果の完成」なのか「作業の遂行」なのかを明確にしましょう。 - 業務範囲と報酬対象を具体的に記載する
何をすれば報酬が支払われるのか、またどの時点で支払いが発生するのかを明確にすることで、不払いリスクを下げることができます。 - 契約類型を記載する
「これは準委任契約である」「これは請負契約である」と明記することで、双方の認識を一致させることができます。法律的にも有効な根拠となります。
5.まとめ 契約書は中身が命
準委任契約と請負契約は、たとえ同じ業務内容であっても、契約の形によって責任や報酬の条件が大きく変わることがあります。そのため、契約名称よりも「契約の中身」が非常に重要です。
トラブルを防ぐためには、「成果物があるかどうか」「業務の成果を保証するのか」といった視点で契約内容を検討すること、そして契約書の内容をできるだけ具体的にすることが不可欠です。
東京深川行政書士事務所では、フリーランスや小規模事業者の方々が安心して業務に取り組めるよう、契約書の作成・チェックを多数手がけてきました。業務の実態に即した契約書づくりで、トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。契約に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
▼ ご相談はこちらから https://panda-gy.com/