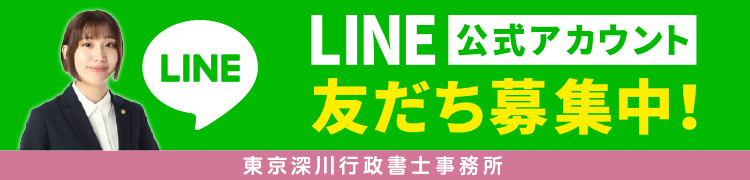介護タクシー開業に必要な手続きとは
こんにちは。東京深川行政書士事務所です。
介護タクシーは、身体障害者や要介護認定を受けた方が、介護関連の資格を持っているスタッフの手助けを受けながら、福祉車両で自宅から病院施設までの通院・移送サービスを行う事業です。
都市部だけでなく地方でも根強い需要が見込まれることから、人気の業種となっています。
本コラムでは、介護タクシー事業立ち上げにあたってのポイントを解説します。
介護タクシーの概要
介護タクシーは、身体障害者や要介護認定を受けた人が、介護資格を持っているヘルパー2級以上のスタッフの手助けを受けながら、福祉車両で自宅から病院施設までの通院・移送サービスを受ける事業となります。
介護タクシー事業者となるためには、「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。
「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って有償で運送する行為をいい、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。
「介護タクシー」は、街で見かける一般のタクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請の方法
(1)許可申請書の提出
道路運送法第5条及び同法施行規則第4条第8項及び第6条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可申請書を営業所所在地管轄の運輸支局に提出します。
申請書に記載する特徴的な内容は次のとおりです。
・経営しようとする一般乗用旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)・業務の範囲(福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲)
福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる者及びその付添人に限定されます。① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
② 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
④ 上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
併せて、道路運送法施行規則第6条第1項第8号~第11号に掲げる書類を添付書類として提出します。
・ 既存法人の場合:定款又は寄附行為(定款にあっては、目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要)
・ 登記簿の謄本(目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要)
・ 直近の事業年度における貸借対照表、役員名簿(常勤、非常勤を記入したもの)
・ 役員全員の履歴書、会社経歴書(沿革)
・ 個人の場合:財産目録、戸籍抄本、履歴書
(2)法令試験及び事情聴取の実施
法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、提出した運輸局で適宜実施されます。
法令試験については、実施日時、場所等を実施予定日の7日前を目途として申請者あてに通知されます。
試験の対象者は申請者本人(申請者が法人である場合は、許可後当該一般乗用旅客自動車運送事業に専従する役員)となります。
出題範囲は次のとおりです。
① 道路運送法
② 道路運送法施行令
③ 道路運送法施行規則
④ 旅客自動車運送事業運輸規則
⑤ 旅客自動車運送事業等報告規則
⑥ 自動車事故報告規則
⑦ その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
設問方式は○×方式、語群選択方式及び簡単な筆記回答方式とされています。
出題数は30問となります。
試験時間は45分です。
合格基準は正解率80%以上(24問以上の正解)となります。
なお、受験の際には、法令集等の持ち込みが認められます。
(3)審査基準に基づく審査
公示基準に基づいて審査が行われ、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
・営業区域
原則として県を単位として設定されているものであること。・最低車両数
1両・福祉輸送サービスに使用する車両
① 福祉自動車② セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車
このほか、一般旅客自動車運送事業と同様な項目に関して審査が行われます。
・ 自動車車庫
・ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
・ 管理運営体制
・ 運転者の人員体制
・ 資金計画
・ 法令遵守に関すること
(4)許可処分
標準処理期間は2ヶ月と定められていますが、各運輸支局にて申請書が受理されてから申請書類に不備のない場合となります。
申請者が補正処理対応を行う期間は、標準処理期間に含まれないため、補正が必要な場合はその処理する期間により標準処理期間を超過することがありますので余裕をもって手続きを行うとともに、行政書士によるサポートが有用です。
(5)許可書の交付
申請書を提出した運輸支局にて交付されますが、注意が必要な点として、許可後、直ちに事業を開始することはできません。
許可書が交付された後に運賃・約款の認可申請等の様々な手続きが必要になります。
(6)運賃・約款の認可申請
運賃の種類は次の種類があります。
・時間制運賃
旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃。・距離制運賃
旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離に応じた運賃。・定額運賃
一定の輸送範囲において、事前に定額を定めて運送の引受けを行う運賃。介護タクシーの特徴として、運賃及び料金の設定は、福祉輸送サービスの実態を踏まえ、送迎サービスの内容等に応じた一定の幅で設定することができるとされています。
また、ケア運賃として、次のような運賃体系も認められています。
・ 時間制運賃を基本として、15分又は30分単位など細分化した時間に対応して設定するもの。
・ 一定の幅で運賃を設定し認可を受け、その範囲内で送迎サービスの内容等に応じて運賃を収受するもの。
・ 一定の輸送範囲において定額運賃を設定するもの。
更に、定額運賃、運賃の割引、運賃の割増及び料金については、運賃改定時以外においても随時申請が行えることとなっていますので、事業を開始した後に収益性に問題が判明した時は速やかに随時申請を行うことにより、事業の継続を図ることが可能です。
(7)運輸開始届
許可書の交付を受けて事業を開始されましたら、運輸開始届を運輸支局に提出する必要があります。
この運輸開始届が受理されることにより、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了したことになります。
まとめ
今回のコラムでは、介護タクシー事業の開始にあたっての手続きを解説しました。
固定顧客が積みあがることで安定的な収益が見込める介護タクシーは、今後ますます注目されることでしょう。
東京深川行政書士事務所では、福祉系事業許認可申請サポートセンターを通じ、福祉業界に精通した行政書士が設立から申請まで一気通貫でお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。